甥っ子の入学祝いを渡すのは一般的ですが、家庭によって考え方はさまざまです。最近では、親戚同士で相談し、贈るかどうかを決めるケースも増えています。
また、お祝いを贈ることで相手に気を遣わせることを避けるため、あえて「渡さない」と決める家庭もあるようです。
とはいえ、甥っ子の入学祝いは一般的な習慣とされているため、贈るべきか迷う方も多いのではないでしょうか?
相場やマナーを知ることで、何を贈ればよいのかが明確になります。悩んでいる方にとって、参考になる内容をお届けします。
甥っ子への入学祝いは必須?贈るべき人の考え方

一般的に、慶事のお祝いは3親等までとされており、甥っ子の入学祝いを贈らないのはマナー違反と考える人もいます。
3親等の関係
| 1親等 | 両親・子ども |
| 2親等 | 祖父母・兄弟姉妹 |
| 3親等 | 叔父叔母・甥姪 |
ただし、兄弟姉妹が多い場合や、贈る側が若く経済的に負担が大きい場合、また親戚付き合いが少ない場合は、「贈らない」という選択をすることもあります。
大切なのは、義務感ではなく、甥っ子の成長を心から祝う気持ちです。
入学祝いを贈る?贈らない?それぞれの意見
甥っ子への入学祝いについては、贈る派と贈らない派で意見が分かれます。
贈らない派の意見
入学祝いが必須だとは思わなかった
甥や姪が多く、すべてに贈るのは負担が大きい
お祝いをしたいが、経済的な事情で難しい
贈る派の意見
入学の機会は限られているので、大切にしたい
金額よりも「気持ち」が重要
甥っ子の喜ぶ顔を見るのが嬉しい
よく会う甥っ子には贈るようにしている
入学祝いは必ず贈るべきものではなく、親戚の人数や関係性を考えながら判断することが大切です。
「お祝いしたい気持ちはあるけれど、金銭的に余裕がない」という場合は、手紙を添えるなどの方法で気持ちを伝えるのも良いでしょう。
大切なのは金額ではなく、お祝いの気持ちです。
もし自分が入学祝いをもらっていない場合は?
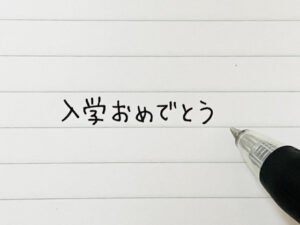
「自分は入学祝いをもらっていなかったけれど、甥っ子には贈るべき?」と悩む方もいるかもしれません。
相手からもらっていない場合、贈る必要はありません。ただし、当時は親戚が若く、経済的な余裕がなかった可能性も考えられます。
また、お祝いを贈ることで相手に気を遣わせたくないと考える人もいるため、それが理由で贈られなかったのかもしれません。
普段から甥っ子と親しくしているなら、現金ではなく、好みに合ったプレゼントを選ぶのも良い方法です。
甥っ子への入学祝いの金額はいくらが適切?押さえておきたいマナー

お祝いごとは頻繁にあるわけではないため、「入学祝いの金額はいくらが適切だったか」と迷うこともあるでしょう。
ここでは、甥っ子に贈る入学祝いの金額相場と、知っておきたいマナーについて詳しく解説します。
甥っ子への入学祝いの金額は?年齢ごとの目安
入学祝いの相場は、進学先によって異なります。以下の表を参考にしてください。
| 学校区分 | 金額の目安 |
| 小学校 | 5,000円~10,000円程度 |
| 中学校 | 5,000円~30,000円程度 |
| 高校 | 10,000円~50,000円程度 |
| 大学 | 30,000円~50,000円程度 |
贈る側が学生や社会人になりたての場合は、5,000円程度と少し控えめにするケースもあります。
あまりに高額な金額を贈ると、受け取る側に気を遣わせることもあるため、負担にならない範囲の金額や品物を選ぶのが理想的です。
また、一度入学祝いを贈ると、その後の進学時にも贈ることが一般的なので、長期的な計画を立てることも大切です。
次の「甥っ子に入学祝いを贈る際のマナー」では、具体的なマナーについて紹介します。
甥っ子への入学祝いを贈る際の4つのマナー
入学祝いを贈る際には、いくつかのマナーを守ることが大切です。
1.入学祝いは入学式の1~3週間前に渡す
2.熨斗(のし)や水引をつける
3.兄弟姉妹で金額を揃える
4.進学ごとに継続して贈る
親戚間の関係を円滑に保つためにも、これらのマナーを意識しましょう。
マナー1:入学祝いを渡す時期は入学式の1~3週間前
一般的に、入学祝いは入学式の1~3週間前に贈るのがマナーとされています。
公立の小学校・中学校の場合は、3月初旬から贈ることが可能です。ただし、受験を経て入学する場合は、合格発表後に渡すのが適切です。
また、3月下旬は入学準備で忙しくなるため、できるだけ避けた方が良いでしょう。
もし入学祝いを渡しそびれた場合は、メッセージカードを添えて贈ると、遅れたことをフォローできます。
マナー2:熨斗(のし)や水引を忘れずに
現金を贈る場合は、赤白の蝶結び(関西の一部ではあわじ結び)の水引がついたのし袋を使用します。
蝶結びは何度も結び直せることから、「繰り返しても良いお祝いごと」に使われるため、入学祝いにも適しています。
表書きには「御入学祝」または「入学御祝」と記載し、贈る側の氏名をフルネームで書きましょう。
品物を贈る場合は、水引が印刷されたのし紙を使用すると便利です。郵送する場合は「内のし」にすると、汚れを防ぐことができます。
マナー3:兄弟姉妹で金額を揃える
親戚間のトラブルを避けるため、兄弟や姉妹がいる場合は、贈る金額を統一するのが理想的です。
金額に差があると、親族内で不公平感が生まれたり、お礼を準備する側にも負担をかけてしまうことがあります。
事前に話し合い、同じ金額を贈ることで、スムーズに対応できます。
マナー4:進学ごとに継続して贈る
一度入学祝いを贈ると、その後の進学時にも贈るのが一般的です。
例えば、小学校の入学祝いを贈った場合は、中学校・高校・大学と、次の節目ごとにも贈ることを想定しておきましょう。
そのため、最初に贈る金額も無理のない範囲で設定することが大切です。
甥っ子の入学祝いにぴったりの贈り物5選

甥っ子への入学祝いとして最も一般的なのは現金ですが、近年では品物を選ぶ人も増えています。
堅苦しさを避けつつ、相手に喜ばれるギフトを選びたい方のために、入学祝いとして人気の贈り物を5つご紹介します。
1.現金
最も選ばれているのが、やはり現金です。
新生活の準備には何かとお金がかかるため、入学祝いとして現金を受け取ると助かるという声が多く聞かれます。
現金なら、学校で必要なものを購入したり、家族で入学を祝う食事会の費用に充てたりと、自由に使えるのが魅力です。
2.図書カード
現金に次いで人気なのが「図書カード」です。
現金だと保護者が必要なものに使うケースも多いため、甥っ子本人が好きな本を自由に選べるようにと、図書カードを贈る人も増えています。
本を読むきっかけになるため、保護者にも好評です。
さらに、ハンカチやメッセージカードを添えると、より気持ちの伝わる贈り物になります。
最近ではQRコード式の図書カードもあり、全国の書店やオンライン書店で使えるので便利です。
3.文房具
入学後に毎日使うものといえば「文房具」です。
消耗品でもあるため、いくつあっても困ることがありません。
名入れができる鉛筆や、甥っ子の好きなキャラクターの文房具セットなど、選択肢が豊富なのも魅力です。
ただし、キャラクターものは学校によって持ち込みが禁止されている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
高校生や大学生に贈る場合は、少し高級感のあるシャーペンなども喜ばれます。息子が大学に進学した際に、8000円のKaweco(カヴェコ)のシャーペンを親戚からプレゼントされました。
自分では絶対に買わない、でも毎日使うものがとてもカッコよくて書きやすいシャーペンだと言ってとても喜んでいました。
4.カタログギフト
保護者からの支持が高いのが「カタログギフト」です。
子ども向けの商品はもちろん、大人向けのアイテムまで掲載されているため、選ぶ楽しさがあります。
最近ではおしゃれなデザインのカタログギフトも増えており、どれを選ぶか考える時間もワクワクするポイントです。
贈る側が品物を選ぶ手間が省け、受け取る側は欲しいものを自由に選べるので、双方にとってメリットの多い贈り物といえるでしょう。
5.目覚まし時計
新生活を迎えるにあたり、必要になるアイテムの一つが「目覚まし時計」です。
特に、小学校への入学を機に「自分で起きる習慣をつけてほしい」と考える保護者も多く、実用的なプレゼントとして人気があります。
朝起きるためだけでなく、勉強時間を管理するのにも役立ちます。
アナログ時計を選べば、時計の読み方を覚える練習にもなり、一石二鳥です。
甥っ子への入学祝いは必要?まとめ
- 入学祝いを贈らないのはマナー違反ではないが、関係性や距離感を考えて判断する
- 親戚間で話し合い、「贈らない」と決めた場合は、必ずしも用意する必要はない
- 自分が入学祝いをもらっていない場合、甥っ子にも贈らなくても問題ない
- ほかの家族も贈る場合は、金額を揃えると良い
- 入学祝いは余裕をもって入学式の3週間前までに贈るのが理想的
- 一度贈ると、その後の進学時にも贈るのが一般的
- 小学校の入学祝いの相場は5,000円~10,000円程度だが、贈る側の状況に合わせた金額で問題なし
- 現金以外にも、図書カードや文房具など実用的な贈り物が喜ばれる
普段あまり交流がない甥っ子に対しては、どのように対応すべきか迷うこともあるでしょう。
そんなときは、一人で決めずに親戚と相談して方針を決めるのがベストです。
何よりも大切なのは、甥っ子の新たな門出を心から祝う気持ち。現金にこだわらず、相手の喜ぶ品物を選ぶのも素敵な方法です。


