教育実習を終えた後、「感謝の気持ちをきちんと伝えたい」と思う方も多いはず。そんなときに重要なのが「お礼状」です。
でも、「いつ出せばいいの?」「どんな内容が正解?」と悩んでしまう方もいるかもしれません。
この記事では、教育実習後にお礼状を出すタイミングや文例、マナーを網羅的に解説します。保育士志望の学生さんから教員志望の方まで、誰でも活用できる内容です。
教育実習後のお礼状の重要性

お礼状を書く理由とは?
教育実習は、未来の教師としての大きな第一歩。その現場でご指導いただいた先生方への感謝の気持ちを、形として残すのが「お礼状」です。
メールや口頭でも感謝は伝えられますが、手紙という形式には「心を込めて書いた」という丁寧さがにじみます。特に教育現場では、礼儀や心遣いを重んじる風土が根強く残っているため、お礼状の存在は非常に大きな意味を持ちます。
教育実習での感謝を伝える意義
実習先では、教員や保育士の先生方が忙しい日々の中で、貴重な時間を割いて指導してくれています。その感謝をしっかり伝えることは、社会人としての基本的な礼儀であり、同時に自分自身の成長にも繋がります。
実習中に得た学びや気づきを、自分の言葉で感謝として伝えることで、より深い学びとして自分の中に定着していくのです。
礼儀としてのお礼状
教育現場においては、「礼儀」が何より重視される価値観のひとつ。
お礼状は、その礼儀を示す一つの行動です。たとえ短い文章であっても、心を込めて書いたお礼状は、相手の印象に強く残るものです。
お礼状の影響力
実習先での評価は、実習期間中の行動だけでなく、その後の対応まで見られていることがあります。
丁寧なお礼状が届いた学生は、「礼儀正しく誠実な人」として記憶され、将来の採用や紹介など、思わぬ形でプラスに働くこともあるのです。
お礼状の出すタイミング
教育実習終了後の最適なタイミング
お礼状は教育実習が終了してから1〜3日以内に出すのがベストです。
実習が終わった直後は、先生方の記憶にも実習生のことが鮮明に残っているため、そのタイミングで感謝の気持ちを伝えると、より強い印象を残すことができます。
遅くとも1週間以内には届くように心がけましょう。早すぎると形式的に見えてしまい、遅すぎると誠意が伝わりにくくなります。
遅れてお礼状を出す場合はどうするか
「忙しくて出しそびれてしまった…」という場合も、出さないよりは出した方が誠意が伝わります。
その際は、文面の冒頭で「ご挨拶が遅くなり申し訳ございません」と一言添えるのがマナー。
誠実にお詫びをしつつ、実習で学んだことや感謝の気持ちをしっかり伝えれば、丁寧な対応として評価されることもあります。
手渡し or 郵送、どちらが良い?
基本的には郵送がおすすめです。
教育実習が終わると、学校や園に立ち寄る機会がなくなるため、郵送がもっともスムーズに届けられます。
ただし、最終日に渡す機会がある場合や、再訪の予定がある場合は手渡しもOK。その場合は封筒に入れたうえで、清潔な封筒・筆記具で丁寧に書くことが大切です。
また、手渡しの場合でも「後ほど郵送します」と言っていた場合には、約束を守る意味でも郵送が望ましいです。
お礼状の書き方基本ガイド

お礼状の構成と必要な要素
教育実習のお礼状には、以下のような構成が一般的です。
- ①宛名:〇〇先生 へ(または園長先生 へ)
- ②時候の挨拶:「晩夏の候」など、季節に合った言葉
- ③自己紹介:実習期間や学校名、自分の名前
- ④感謝の言葉:ご指導いただいたことへの感謝
- ⑤学びの振り返り:どんなことを学んだか、どのように今後活かすか
- ⑥今後の抱負:教職・保育士への決意や展望
- ⑦結びの挨拶:「貴園のご発展をお祈りいたします」など
- ⑧署名:学校名・学部・氏名
この構成に沿って書くことで、読みやすく、丁寧な印象のお礼状になります。
時候の挨拶の選び方
時候の挨拶は、手紙の冒頭に使う季節感ある言葉です。
以下は月ごとの例です。
- 5月:新緑の候/薫風の候
- 6月:梅雨の候/初夏の候
- 7月:盛夏の候/酷暑の候
- 8月:晩夏の候/立秋の候
- 9月:初秋の候/秋涼の候
形式にこだわりすぎず、「暑い日が続いておりますが、先生方におかれましては〜」といった口語的な挨拶でも丁寧さは十分伝わります。
具体的な文例と手書きのポイント
以下は基本的な文例です。
拝啓 晩夏の候、貴園の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたびは、〇月〇日から〇月〇日までの教育実習におきまして、大変お世話になりありがとうございました。
〇〇先生をはじめ、先生方の温かいご指導のもと、多くの学びと貴重な経験をさせていただきました。
中でも〇〇の場面では、子どもたちと接する難しさと楽しさを肌で感じることができ、自分の目指すべき保育士像を見つめ直す機会となりました。
この経験を糧に、今後さらに努力を重ねてまいります。末筆ながら、貴園のますますのご発展と、先生方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
敬具〇〇大学△△学部 氏名
手書きが基本ですが、字に自信がない場合でも、丁寧に書くことを意識すれば問題ありません。
鉛筆ではなく、万年筆や黒のボールペンで、行間を詰めすぎず読みやすさを重視しましょう。
お礼状に使えるテンプレート

シンプルなテンプレートの紹介
教育実習後のお礼状は、構成とマナーさえ押さえていれば、シンプルでも心のこもった手紙になります。以下のテンプレートを元に、ご自身の体験や感謝の言葉を加えてみてください。
拝啓 〇〇の候、貴校(または貴園)の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
このたびは、〇月〇日より〇月〇日までの教育実習において、大変お世話になりありがとうございました。
先生方からの温かいご指導のもと、実際の教育現場を体験することで、多くの学びと気づきを得ることができました。
今回の経験を今後の進路にしっかりと活かしてまいります。末筆ながら、貴校の益々のご発展と先生方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
敬具
〇〇大学△△学部 氏名
保育士向けお礼状テンプレート
保育園での教育実習を終えた方に適した、子どもとの関わりや保育内容を盛り込んだテンプレートです。
拝啓 初秋の候、貴園の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたびは、〇月〇日からの教育実習において、大変お世話になり、誠にありがとうございました。
子どもたちと関わる中で、笑顔の裏にある先生方の細やかな配慮や観察力の大切さを実感いたしました。
また、〇〇先生から教わった保育の在り方は、今後の目標となりました。この貴重な経験を糧に、立派な保育士となれるよう、日々努力を重ねてまいります。
今後ともご指導賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
〇〇大学△△学部 氏名
学校先生向けお礼状テンプレート
小学校・中学校・高校などの先生方に向けた、学習指導や生徒対応への感謝を伝える形式です。
拝啓 〇〇の候、〇〇先生におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
このたびの教育実習では、先生からの丁寧なご指導と温かい励ましをいただき、心より感謝申し上げます。
授業の工夫や生徒への接し方を間近で学ばせていただき、自分の理想とする教師像が明確になりました。
特に、〇〇の授業でのご対応や言葉かけが印象に残っております。今後も学びを深め、先生方のような信頼される教師を目指してまいります。
重ねて御礼申し上げるとともに、貴校のご発展を心よりお祈り申し上げます。敬具
〇〇大学△△学部 氏名
共通するマナーと注意点
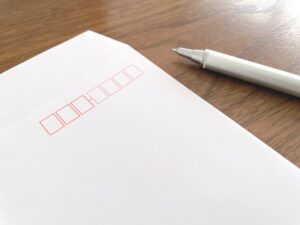
誤字脱字に注意!
どんなに気持ちのこもったお礼状でも、誤字脱字があると印象が損なわれてしまいます。
特に先生の名前や学校名・園名は絶対に間違えないようにしましょう。書き終えたら必ず見直し、可能であれば第三者にチェックしてもらうのもおすすめです。
手書きの場合は修正液の使用は避け、書き直すのが礼儀とされています。
シンプルに伝える文章のコツ
文章は、簡潔かつ丁寧にが基本です。
回りくどい表現や、感情の起伏が大きすぎる文面は、読み手にとって負担になることもあります。
「伝えたいことを一文に一つ」意識しながら、わかりやすく丁寧に構成しましょう。
礼儀を重んじた表現の選び方
教育の現場では、丁寧語・敬語の使い方も見られています。
たとえば「ありがとうございました」ではなく「誠にありがとうございました」、「教えてもらいました」ではなく「ご指導いただきました」など、敬意が伝わる表現を意識しましょう。
また、「嬉しかったです」ではなく「ありがたく感じております」など、やや改まった言い回しが好印象を与えます。
お礼状を書く際のコラム

実習先の園長先生への感謝の具体例
たとえば保育園での教育実習中、園長先生から職員間の連携や運営の裏側について直接お話をいただくこともあります。
そのような経験をお礼状に盛り込むことで、単なる形式的な文章ではなく、実体験に基づいた心のこもったメッセージになります。
園長先生が実習生一人ひとりに声をかけてくださったことや、昼休みに保育の方向性についてお話しいただいたことが特に印象に残っております。貴重なお時間を割いてくださったことに、心より感謝申し上げます。
保育現場での学びをどう伝えるか
お礼状には、単なる「ありがとうございました」だけでなく、どんな学びがあったか、どう成長できたかも書き添えると、相手にとっても励みになります。
子どもたちが泣いたり笑ったりする中で、言葉ではなく「気持ちをくみ取る力」が大切だと学びました。先生方の言葉の選び方や間の取り方から、人として大切な在り方を教えていただきました。
学生の成長に繋がるお礼状の作成
お礼状を書く過程そのものが、自分の成長を振り返る機会になります。
学んだことを言語化することで、自分がどんな価値観や理想像を持っているのかが見えてきます。
つまり、お礼状は「感謝を伝える」だけでなく、実習の締めくくりとして自己理解を深める手段でもあるのです。
実習を通して「理想の保育士像」が明確になり、これからの目標がより具体的になりました。この気づきをくださった先生方に、改めて感謝申し上げます。
お礼状を送る際のその他の考慮点
封筒の選び方と記載内容
お礼状は白無地の封筒が基本です。柄物や派手なカラー封筒は避け、シンプルで清潔感のあるものを選びましょう。
封筒の表面には、宛名を丁寧に縦書きで書きます。宛先は「〇〇先生」または「〇〇園長先生」と敬称を忘れずに。
裏面には、自分の名前・大学名・住所を記入します(差出人欄)。これも縦書きが望ましく、ボールペンや万年筆で書きましょう。
便箋や万年筆を使った際の印象
便箋も白地または淡い色の罫線入りがおすすめです。キャラクターやカラフルなデザインは、ビジネスマナーとしてふさわしくありません。
筆記具は黒の万年筆やゲルインクペンが◎。インクのにじみやかすれに注意しながら、丁寧に書くことが最も大切です。
丁寧に手書きされたお礼状は、誠意がしっかりと伝わるため、受け取った相手にとっても印象深いものになります。
教師と生徒の関係における配慮
教育実習では、生徒と先生という関係の中で接していたため、お礼状もあくまで「一教育実習生」としての立場を忘れず、敬意を持った文面を心がけましょう。
また、フランクすぎる表現や過剰な私的感情の記述は避け、丁寧で節度ある言葉選びが求められます。「人としての礼節を学ぶ」機会として、最後まで誠意ある対応を心がけましょう。
まとめ:お礼状で伝える感謝のメッセージ
お礼状の効果的な活用法
教育実習のお礼状は、単なる形式的な手紙ではなく、自分の思いや学びを言葉にして届ける、人生のステップアップの一環です。
誠意を込めた一通の手紙が、実習先との良好な関係を築き、将来の進路に繋がる可能性もあります。
「お世話になったから感謝したい」という気持ちを、丁寧な文章で表現してみましょう。
次のステップへ繋がるお礼状の伝え方
お礼状を丁寧に書いた経験は、これから教員・保育士を目指す上での基礎的な社会人マナーにも直結します。
また、お礼状を出すことで、実習を「受けた」だけでなく、「しっかり締めくくった」という意識を持てるのも大きなポイントです。
教職に必要な「報連相(報告・連絡・相談)」の力を、こうした場面で身につけておくと、現場に出たときに役立ちます。
お礼状を介して学ぶことの重要性
教育実習を通じて得られた学びや感謝の気持ちは、一人の人間としても大きな財産です。
お礼状を書くことで、自分が何を感じ、どう変化したのかを客観視するきっかけにもなります。
手紙1枚が、未来の自分にとっても、読み返したくなる原点になることもあるでしょう。
教育実習後は、感謝の気持ちを形にして伝える絶好のチャンスです。
ぜひこの記事を参考に、丁寧で心のこもったお礼状を作成してみてください。


